【PARKS取り組み】単元対策と問題傾向対策は全く別物です!

進学塾PARKSのご紹介
進学塾PARKSセンター南校は、小学生〜高校生を対象に、代表が授業から進路指導までを一貫して行う定員制の進学塾です。制限なく学習してほしいとの想いから個別指導の2-3教科の値段で5教科(もしくは受験科目全て)を提供し、毎日実施される定着授業は受講し放題です。本日は塾として最も根幹といえる、試験対策について伺いました。
インタビューする先生

千葉隼也先生 進学塾PARKSセンター南校代表
偏差値は35から早稲田大学に合格した苦労人。在学中から集団塾と個別指導塾で講師を勤め、大手学習塾に入社。小学生から高校生まで数多くの生徒を合格に導くとともに、オンラインコース、教務、システムなどを歴任。その後リクルートに入社し、教育機関向けスタディサプリの企画担当として事業企画や営業推進を担当。2024年6月、進学塾PARKSセンター南校を開校。
学習塾を探している方にとって、「しっかりとした対策をしてくれる塾かどうか」は非常に重要なポイントです。その際によく聞くのが「単元対策」や「傾向対策」といった言葉です。しかし、これらが具体的にどう違うのか、なぜ両方が必要なのかを理解されている方は案外少ないかもしれません。
この記事では、まず「単元対策」とは何か、次に「問題傾向対策」とは何かをわかりやすく解説したうえで、なぜ傾向対策は難しいのか、そして当塾がどのようにそれを実現しているのかをお伝えします。
※定期試験を中心にお伝えしていますが、入試も同様です。
単元対策と問題傾向対策とは?
-「単元対策」とは何でしょう?
千葉先生 「単元対策」とは、学校の教科書に基づき、特定の単元に絞って理解・演習を進める学習のことを指します。これはいわば“基礎の土台作り”であり、どの教科でもまず最初に行うべき基本的な学習方法です。たとえば、中学1年生の数学では「正の数・負の数」「文字式」「方程式」といった単元が順番に学ばれます。この一つひとつを理解し、定着させることで、教科全体の学力が底上げされていきます。英語であれば「be動詞」「一般動詞」「疑問詞」「助動詞」など、基礎文法を段階的に学ぶことが重要になります。
多くの塾や学校では、この単元ごとの指導が基本になります。教科書やワークを使いながら、順を追って学ぶことができるため、体系的に理解しやすく、また指導する側にとっても教えやすいのが特徴です。
-「単元対策」する上で気を付けるべきことは何でしょうか?
千葉先生 実際のテストでは、出題される問題が単元ごとに整理されていることも多く、「この問題は比例の知識が問われている」「これは関係代名詞を使えれば解ける」など、どの単元が問われているのかが明確な場合もあります。こういった基礎問題は絶対に落とせないので、単元ごとの基礎力をつけることは学力の土台づくりにおいて欠かせない要素であり、どの学習段階でもまず優先すべきです。
定期試験で60点に届かない生徒の場合は、ほとんどの場合この単元ごとに理解に不足があることが多いです。同じ問題でも繰り返し何でも実施して、まずはこれは「○○を利用する問題」と提示されたうえで、確実に解けるようにすることで、点数UPが期待できます。逆にいえば、高得点を目指さない生徒は学校のワークや基礎問題集を繰り返しやることで一定の点数UPが望めます。
一方で都筑区の中学校の定期試験は難易度が高いため、ある程度の点数まで伸びると単元対策だけでは伸び悩むということが発生します。
-「問題傾向対策」とは何でしょう?
千葉先生 「問題傾向対策」とは、テストや入試において“どのような形式・構成で出題されるのか”を分析し、それに合わせた練習や思考力のトレーニングを行うことを意味します。学校のテストや高校入試では、必ずしも単元別にわかりやすく出題されるわけではありません。複数の単元を組み合わせた応用問題、文章題、資料を読み取る問題、時間制限の中で処理すべき設問、さらには設問の意図を読み取る「読解力」など、さまざまな要素が絡み合っています。
たとえば、社会科の入試問題では「地理+統計資料の読み取り+記述力」を一つの設問で問うようなものが出題されることもあります。また、国語では、選択肢の選び方が極めて似ていて、文脈読解の精度が問われるケースも多く見られます。
こうした“複合的な問題”に対応するには、「単元を理解している」というだけでは不十分なのです。どんな出題のされ方をするか、どのような設問パターンが頻出か、どの分野の知識が融合されやすいかなど、「問題の傾向」を把握した上で、それに慣れる練習を積むことが必要不可欠です。
さらに重要なのは、「同じ教科・単元であっても、学校によって出題のされ方がまったく違う」という事実です。たとえば、同じ「比例」の問題でも、A中学校では単純な計算中心、B中学校では文章題やグラフを用いた出題形式が中心、というように“傾向”は学校ごとに異なります。
このような実戦形式の違いに対応できるようになるためのトレーニングが、「問題傾向対策」です。
問題傾向対策まで踏み込んだ塾は少ないです
-「問題傾向対策」の難しさとは何でしょうか?
千葉先生実は、多くの学習塾が単元対策は得意としていますが、問題傾向対策まで踏み込めている塾はそれほど多くありません。なぜなら、傾向対策には「高度な分析力」と「柔軟な対応力」が必要だからです。
単元対策は、教科書や塾用教材に沿って進めれば、ある程度まで同じように全生徒に指導できます。一方、傾向対策は、「生徒の通う学校」「科目」などによって対策内容が大きく変わるため、自社で問題を作成する必要があります。例えば、茅ケ崎中の場合は英語の並び替え問題は、単純な問題ではなく、いわゆる「一語不要問題」といい。選択肢の中に利用しないこ言葉が含まれます。こういった問題は一般的な問題集では応用のページに数問用意のある程度で、なかなか慣れることができません。
また、生徒の側にも負担がかかります。傾向対策では単純な暗記では通用しません。問題文を読み解く力、複数の条件を整理する力、自分の言葉で書き表す力などが問われるため、思考力や応用力を育てる学習が必要になります。
-問題傾向対策をする上で大切なことは何でしょうか?
千葉先生1点目は、単元学習が完璧であることです。もちろん100%でなくても傾向対策は実施してもいいのですが、単元学習に抜け漏れがあればまずはそちらの穴を補填することが大事です。傾向は理解しつつも肝心な解く能力がなければいくら傾向分析をして解けるようにはなりません。たとえば、毎回教科書のテーマの類題として3文の英作文が出るとわかっていても、「旅行の計画を立てる」がテーマとして、旅行という英単語が分からない場合は得点できません。
2点目は、繰り返き、パターンに慣れることです。こういった問題は○○から解く!といったやり方自体そのものを暗記してほしいのです。例えば社会の正誤問題では、間違っている部分に線を引く等ミスを最小限にする解き方が存在します。PARKSでは指導もしますが、一人ひとり自分にあったやり方を見つけることも大切です。
PARKSはオリジナルで問題作って対策してます!
-PARKSではどうやって対応しているのでしょうか。
千葉先生1点目は、定期試験の回収と分析です。もちろん同じ問題や傾向が続くとは限りません。しかし、私版の問題と定期試験にはやはり差があることは事実です。私が申し上げるのも大変おこがましいですが、学校の先生の試験はとても良問で考えられた試験です。そこを徹底的に分析することは大切です。
2点目は当塾では、こうした「問題傾向対策」の重要性を早くから認識し、独自の指導システムを構築してきました。その中核となっているのが、「傾向対応型オリジナルプリント」です。
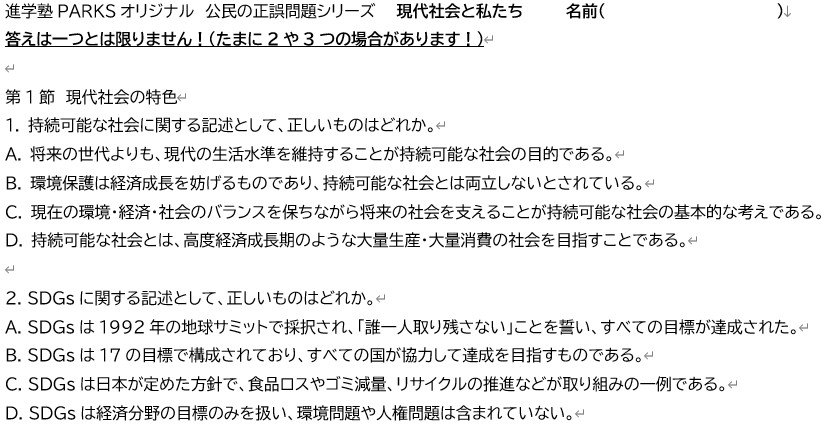
当塾では、各中学校の過去の定期テスト問題を綿密に分析し、「どの単元がどのような形式で出題されるか」「記述問題は何文字程度が多いか」「出題者が重視している観点は何か」といった出題傾向を把握しています。これにより、たとえば茅ケ崎中の3年生には「図表読解+記述型問題」が多く出題されているため、それに対応した演習プリントを重点的に取り入れます。一方、新羽中3年生では新しい英単語はほとんど出ないので、文法や記述問題を練習するプリントを用意しています。
加えて、生徒ごとの到達度に応じてプリントの内容を細かく調整しています。たとえば「記述問題で書く量が少ない生徒」には書き方のテンプレート付きプリント、「計算ミスが多い生徒」には基礎プリントなど、生徒に個別最適な学習を提供しています。つまり、当塾のプリントはただの「問題集」ではなく、傾向に合わせて作るのです。
-最後にメッセージをお願いします。
千葉先生まずは学校のワークや塾の授業を通じて単元の学習は完璧にしましょう。それだけで60点以上は目指せます。そこからは思考力含めた自分との戦いです。傾向をしっかり理解し、フットワーク軽くたくさんの問題を解く姿勢が必要です。PARKSは通塾し放題にしているので、たくさん自習室も利用し、成績を伸ばしていきましょう。今回は定期試験をベースにお伝えしましたが、入試対策も同様です。


